TOPPANホールディングス株式会社では、2024年よりMiletosの経費精算AI「SAPPHIRE(サファイア)」を本格導入し、通勤費の実費精算およびリモートワーク手当の支給業務の大幅な見直しを実施しました。
交通系ICカードの実績、勤怠データ、入退館記録を組み合わせた“実在性のある支給判定”を可能とするSAPPHIREの仕組みにより、社員の申請負担を極小化しつつ、不正や誤申請を排除した制度運用を実現。加えて、給与支給となる通勤費と、経費精算に該当する交通費を一元的に処理できる点も評価され、制度の透明性・公平性を保ちながら、業務の効率化と統制強化の両立が図られています。
本記事では、制度設計・システム設計の両面で本プロジェクトをリードされたTOPPANホールディングス人事労政本部の諸岡様、上條様に、導入の背景や成果、今後の展望まで詳しくお話を伺いました。
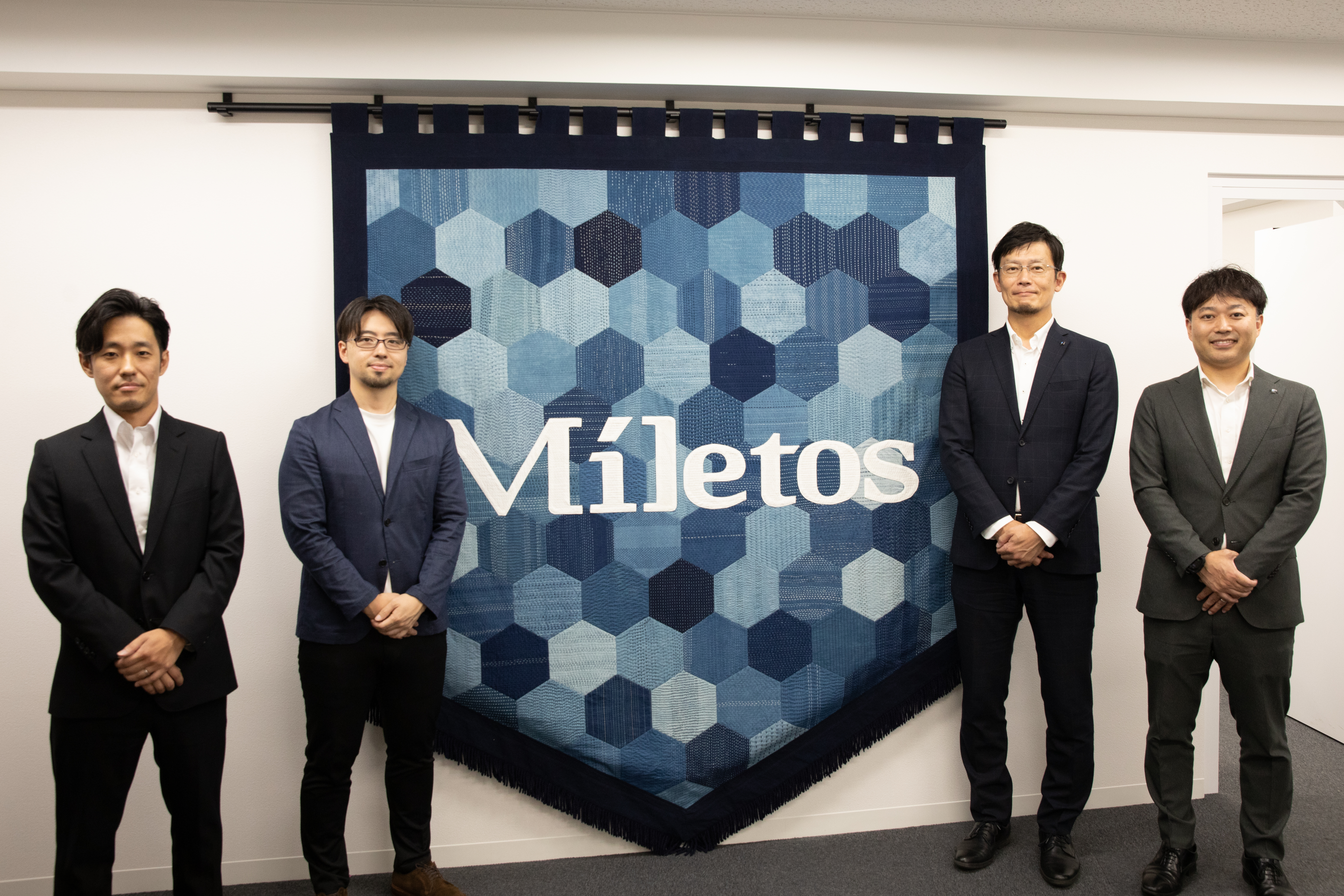

TOPPANホールディングス株式会社
人事労政本部 労政部
諸岡 寛治 様

TOPPANホールディングス株式会社
人事労政本部 総務部
上條 智矢 様

Miletos株式会社
代表取締役社長 兼 CEO
髙橋 康文

執行役員 SAPPHIRE事業部 事業部長
宮村 知秀
- 狙い
-
- リモートワーク制度の開始に伴う在宅勤務手当を統制の取れた形で効率的に支給したい
- 定期代支給の廃止に伴う通勤費の実費精算のプロセスを効率化したい
- 給与として支給される通勤費と、経費精算となる交通費を同一システムで処理したい
- 効果
-
- 実績に基づくAI処理により、社員の申請なしで実在性の高い在宅勤務手当支給が実現
- 社員が希望する経路で、通勤費と交通費を同一システム上で自動処理できるように
- 社員側での入力や申請といった手間を最小限に抑えつつ、運用上の正確性と効率性を確保
通勤交通費と在宅勤務手当の見直しを進めていたタイミングでSAPPHIREを知った
髙橋
-
まずは、今回のプロジェクトでどのような役割を担われたのか教えていただけますか?
諸岡様
-
私たちはTOPPANホールディングスの人事労政本部に所属しておりまして、私は労政部として制度設計を担当しています。今回のプロジェクトでは、新たな勤務制度に対応した支給制度の設計や社内調整、全社的なルール整備を担いました。

上條様
-
私は総務部で、通勤交通費を含む社員の移動関連の運用を担当しています。SAPPHIRE導入プロジェクトにおいては、本社の立場から業務要件の整理やシステムの運用設計を担いました。
髙橋
-
ありがとうございます。今回SAPPHIREを導入するに至った背景について、もう少し詳しくお伺いしたいのですが、弊社にお問い合わせいただいたきっかけはどのようなものだったのでしょうか?
上條様
-
ちょうど、通勤交通費と在宅勤務手当の見直しを進めていたタイミングで、社内でも情報収集を進めていました。そんな中、2021年に、当時は労政部長だった奥村(現・人事労政本部長)が、花王様のSAPPHIRE活用事例の記事を見つけ、Miletosさんにご連絡を差し上げたのが最初の接点でした。そこから、SAPPHIREで本当に自社のやりたいことが実現できるのかどうか、実データを用いた精度検証を実施しました。一定の精度が確認でき、「これなら制度運用に耐えうる」と判断し、正式に要件定義フェーズへと進みました。
リモートワークの制度化により、通勤費の実費精算とリモートワーク手当支給の両方を自動化できるシステムが必要だった
髙橋
-
定期代の支給を廃止し通勤費を実費精算に切り替え、さらにリモートワーク手当の支給も始めるというのは、大きな制度変更だったと思います。その制度変更に伴い、どのような課題が発生したのかお聞かせください。
上條様
-
以前は、6か月定期の金額を算出し、それを給与システムへ連携する運用を行っていました。しかし、リモートワークの浸透に伴い、実際の出社と通勤費支給の整合性が取れなくなりつつあり、公平性を欠くとの声が上がるようになりました。たとえば、週に1〜2回しか出社しない働き方の場合、従来の定期代支給を続けると企業側の負担が過大になる一方で、社員の実態に即さない支給が行われることになっていたのです。
諸岡様
-
また、在宅勤務にかかるコストに対して、社員の自己負担が続くことも問題視されていました。そこで、出社頻度に応じた在宅勤務手当(リモートワーク手当)を支給する制度を新たに設けたいと考えたのですが、手当についても通勤費についても、社員に毎回申請させる運用では、申請ミスや不正のリスクもありますし管理側の確認作業も煩雑になります。そこで、通勤費の実費精算とリモートワーク手当を自動で処理できるようなシステムが必要だと強く感じていました。

髙橋
-
実際に以前使われていたシステムはどのようなものだったのでしょうか?
諸岡様
-
定期代の算出については、社員が直接操作するようなシステムは使っておらず、総務部門が定期代の算出や通勤経路の確認を行うための社内システムを利用していました。6ヶ月定期の金額を自動計算し、それを給与システムへ連携するような運用でした。
上條様
-
ここにも課題感がありました。通勤経路について、社員側が自由に経路を選べる仕組みではなかったため、「本人が希望する経路」と「会社が認める経路」が一致しないことも多く、その点については以前から課題となっていました。通勤費の実費化を機に、社員が自身で経路を選択できる仕組みを実装したいと考えていました。
「申請負担の極小化」と「不正な申請を防ぐ」という両方を叶えられるのはSAPPHIREだけだった
髙橋
-
その課題を解決できるシステムとして、SAPPHIREを選んでいただいたわけですね。数ある選択肢の中で、SAPPHIREを選んでいただいた理由はどういった点だったのでしょうか?

上條様
-
一番大きな決め手は、交通系ICカードの利用実績、勤怠データ、そして入退館記録という三つの実績データを自動で突合し、社員の申請なしでリモートワーク手当と通勤費の支給を判定できるという点です。これによって、社員側での入力や申請といった手間を最小限に抑えつつ、運用上の正確性と効率性を確保できると感じました。
諸岡様
-
実際、同様のフローを実現できる仕組みは、他に見あたりませんでした。多くの製品が「社員の申請を前提」としており、実質的には運用上の課題を根本的に解決できないと感じました。その点、SAPPHIREのように、実績データを元にシステム側で自動判定できる仕組みは、私たちが思い描いていた「ミスを起こさせない制度運用」に非常に近いと感じました。また、SAPPHIREでは通勤費の支給に使うICカードの読み取り機能を活用することで、以前は他の経費精算システムを利用していた近郊交通費の精算もあわせて自動化できる見込みが立ち、最終的な決め手になりました。
上條様
-
SAPPHIREでは、支給対象が経費精算なのか給与支給なのかを自動的に判断し、それぞれ適切な処理方法で仕分けてくれる機能がある点も魅力でした。たとえば、会社までの通勤費やリモートワーク手当は給与として支給される一方、拠点間の移動などの交通費は経費精算として処理してくれます。ルールが異なる支給項目を同じ仕組みの中で自動的に分けて処理してくれることで、経理や給与計算業務における人的ミスの防止にもつながると考えましたし、実際に導入後の業務負荷も極小化されました。
柔軟に対応できるSAPPHIREの仕様が大きな助けになり、個別事情にも対応できた
髙橋
-
今回、SAPPHIRE導入にあたっては、どのような体制でプロジェクトを進められたのでしょうか?
諸岡様
-
今回の制度設計には多くの部門が関わる必要がありました。そのため、私たち人事労政本部をはじめとして、財務部門、情報システム部門が連携し、タスクフォースを組んでプロジェクトを進めました。
宮村
-
定期的に開催されるそれぞれの部署の分科会にMiletosも参加させていただき、「社内の運用はこうありたい」というTOPPANホールディングス様のご要望と、「システム的にはこういった制約がある」というMiletos側の意見を擦り合わせ、調整を重ねていきました。SAPPHIREは設定の自由度が高いぶん、制度そのものの再設計と並行して、運用ルールの具体化にも丁寧に取り組んでいただきました。

上條様
-
たとえば全国に拠点があるので、勤務地によって通勤手段も異なりますし、自社バスの運行がある拠点もあります。また、社員によっては健康増進の観点でひと駅前で降りて歩くなど、経路が複雑になっている場合もあるんです。あとは入退館データが取得できない拠点もあったりなど、そういった現場の個別事情をどう取り扱うか、大変多くの細かいケースをひとつひとつ洗い出しながら検討を重ねました。結果として、柔軟に対応できるSAPPHIREの仕様が大きな助けになりました。
高橋
-
運用開始後の反応はいかがでしたか?
上條様
-
2024年から本格運用を開始しましたが、スムーズに立ち上げることができました。社員からは「ICカードを使い、近郊交通費を含めワンストップで精算されるのは楽」「申請漏れをシステムが警告してくれる」といった声が多く寄せられました。大きな制度変更でしたが、社員からの問い合わせ件数も日を追うごとに大幅に減少しています。
諸岡様
-
リモートワーク手当の支給を望む声は以前からありましたので、効率的かつ統制の取れた形で支給を開始できた点は大きな成果でした。また、社員が通勤費と交通費の処理、およびリモートワークの申請を同じシステム上で一元的に行えるようになったことで、利便性も大きく向上したと感じています。
高橋
-
二年近くにも及ぶ大きなプロジェクトでしたが、制度設計から導入、そして運用まで、長期にわたるプロジェクトをご一緒できたことを大変光栄に思います。引き続き、運用改善・機能拡張など、パートナーとして伴走してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
